ある泊地で、どこかの大学の外洋帆走部の部員さんが乗るお船と隣り合わせた。
そこで強烈な違和感を覚えたのが、港ですれ違う度に、彼ら彼女らが、ことごとく目を伏せて目線を合わせないようにしてすれ違っていく事だ。
最初2−3人はこちらから声を掛けてみたのだが(もちろんご挨拶は返してくれます)、ちょっと興味が湧いたので、何人ぐらい挨拶してくるかなと思って、その後はじっと観察しながら黙ってすれ違ってみたのだが、結果的に、一人も向こうからは挨拶してくれなかった(2日間で都合10人ぐらいとすれ違った)。それでもOBさんが来られた時には皆んな大きな声で挨拶していたので、彼ら彼女らがコミュ障というわけでは無いのだろう。因みに家内にも同じ態度だったらしいから、私の人相風体が悪すぎるからではない(と思う)。
近頃は、小学生にも知らない人に声を掛けられたら返事しないで逃げろと教えるそうだがら*、若い人は挨拶なんかしないのがデフォルトなのかも知れぬが、その是非は別として、シーマンシップ的には、それはまずいんじゃ無いかと思う。
ここでいうシーマンシップには、精神論的な意味を全く含んでいない(ましてや若者は若者らしくハキハキ挨拶しましょうなんて言うのでは全く無いので誤解しないでほしい)。シンプルに船の運用術とかロープワークとかそういうものと同じレベルで、シーマンなら必ずするような、決まりきったお作法や立ち居振る舞いの事である。
船乗りは古今東西、初めての港に入る機会が多い。港の人達から見れば、その船が、交易がしたいのか、補給がしたいのか、はたまた海賊をしに来たのかわからない訳だから、しっかり身構えて、いざとなれば戦えるように準備をして出迎えるだろう。だから、船長は出迎えた人に、まずはにこやかに挨拶をして相手の警戒を解かなければならない。
船員同士でも同じこと。隣の船でもその船から降りてきたヤツが、敵として排除すべき対象なのか、同じ海の仲間なのか、じっと観察していることだろう。だから、まずはにこやかな挨拶からだ。
港では、誰彼構わず、まずは大きな声で挨拶する。これは、「私は皆さんの敵ではありませんよ」と宣言して回るということなのだ。
19世紀の帆船とヨットは違うでしょうと言うかもしれないが、ちょっと考えてみよう。ヨットで漁港に入るとする。港の人たちは、こいつはきちんとルールを守って正しい振る舞いのできる、仲間として受け入れてやって良い連中なのか、それとも、人迷惑を顧みず夜中まで大騒ぎし、挙句は港にこっそりゴミを捨てていくような連中なのか、半ば不安、半ば疑心暗鬼で眺めているだろう。だから最初にすることは、まず礼儀正しくご挨拶をすることだ。目を合わせて、はっきりと相手に自分の顔を認識させることで、「こいつは心に恥じるところはない。だから悪いことはしない」という安心感を与えることができる。それは19世紀と21世紀で何ら変わるところが無い。
たとえ普通の若者は知らない人に挨拶なんかしないのだとしても、ヨット乗りは挨拶できなければならない。あくまでシーマンシップ、つまり海上生活の知恵として、そしてヨット乗りらしい振る舞いをするという意味でである。
* 今はそういうところまで来ているのねという例:
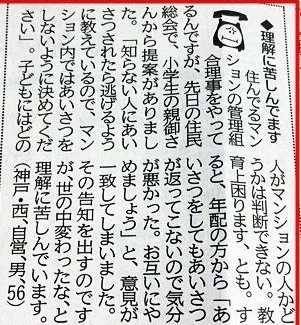



コメント